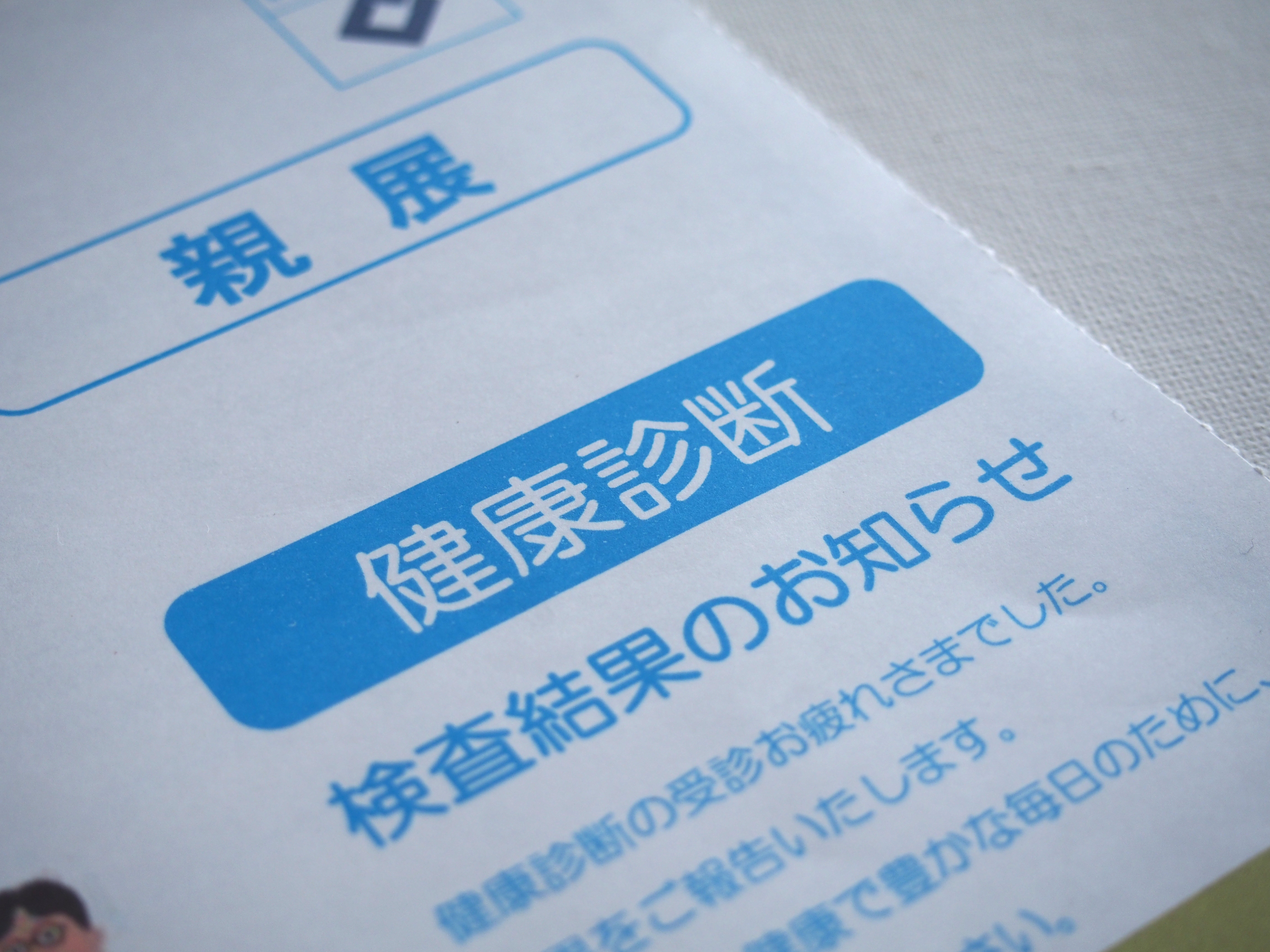- コラムタイトル
-
生命保険で節税できる? 知らなきゃ損する保険料控除の仕組み
- リード
-
生命保険に加入していると年末調整または確定申告を行うことで「生命保険料控除」を受けることができます。しかし「どのくらい税負担が軽減されるのか」について具体的に把握している人は意外と少ないかもしれません。本コラムでは、生命保険料控除の仕組みや対象となる保険の種類、具体的な控除額について解説し、節税メリットを活用する方法を紹介します。
- コラムサマリ
この記事は約5分で読めます。
1.生命保険料控除の基本
2.控除額と節税効果
3.生命保険の選び方
- 本文
-
生命保険料控除とは?基本の仕組み
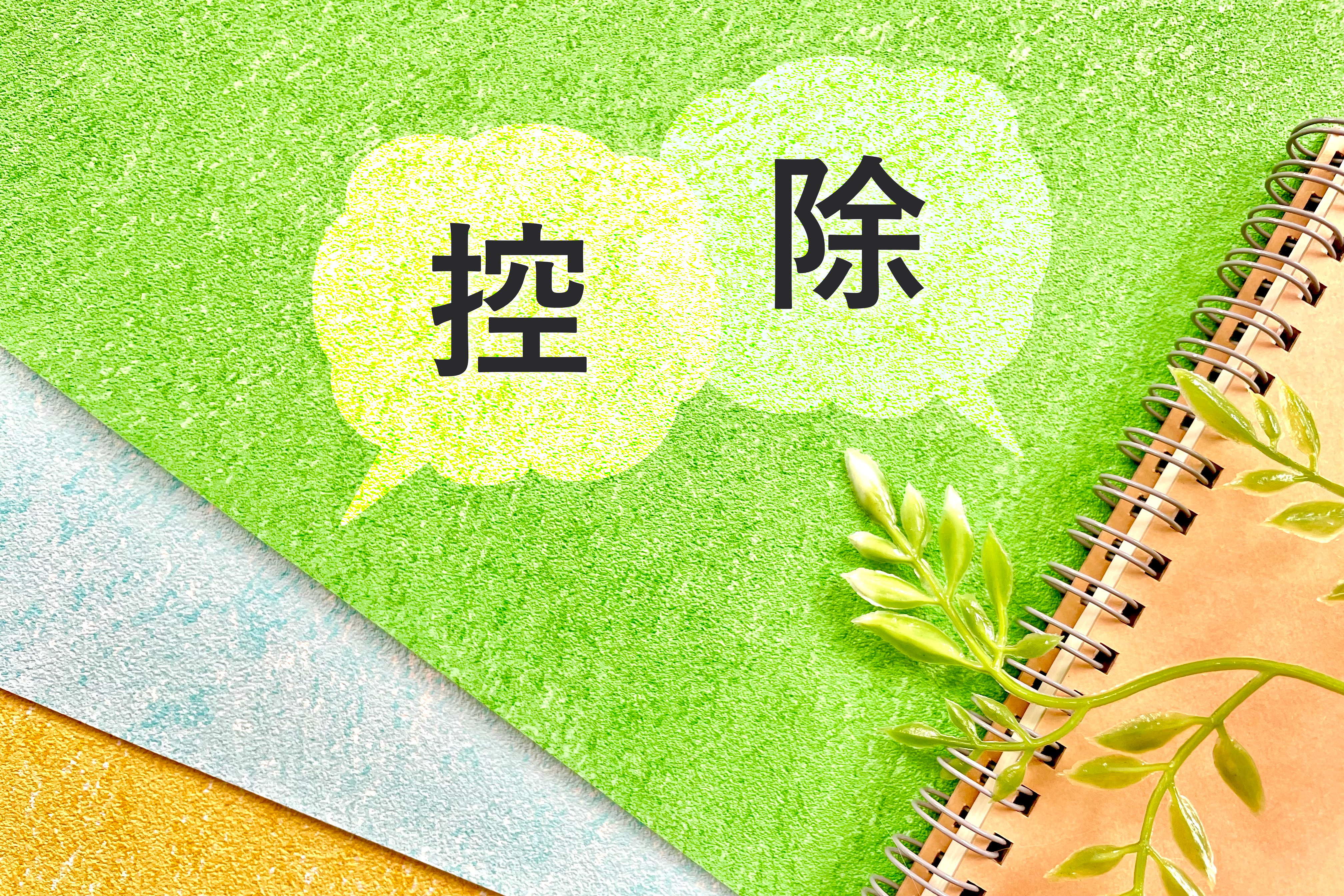
生命保険に加入している人は、支払った保険料の一部が所得控除の対象となるため、税負担の軽減が可能です。年末調整や確定申告の際に適用されるこの制度をうまく活用することで、節税効果を実感できるでしょう。ここでは、生命保険料控除の仕組みと対象となる保険の種類について解説します。
生命保険料控除の概要
生命保険料控除は、納税者が支払った生命保険料の一定額を所得から差し引ける制度です。基本的に生命保険料控除で課税対象となる所得が減るため、最終的に納める税額が少なくなります。多くの会社員の場合、生命保険料控除は年末調整で手続きするため、確定申告しなくても節税の恩恵を受けることができます。
ただし所得控除を受けるためには、対象となる保険に加入していることが条件です。また年末調整で生命保険料控除を申請しなかった場合は、確定申告で手続きを行うことで控除を適用できます。課税所得が減ることで、所得税や住民税が軽減され、家計の負担を和らげる効果が期待できます。
控除の対象となる保険の種類と主な特徴
生命保険料控除の対象となる保険には、大きく分けて3つのカテゴリーがあります。それぞれの保険の特徴や適用条件を理解することで節税対策としての活用が可能です。以下の表に3つの保険の概要をまとめました。
保険の種類
主な特徴
控除対象となる条件
一般生命保険
死亡保障を目的とし、万が一の際に遺族に保険金が支払われる
終身保険・定期保険・収入保障保険など
介護医療保険
病気やケガによる医療費の負担を軽減するための保険
医療保険・がん保険・介護保険など
個人年金保険
老後資金の積み立てを目的とした保険
一定の契約条件を満たした年金保険
これらの保険は、それぞれに異なる生命保険料控除の枠が設けられているため、組み合わせれば最大限の節税効果を得ることができます。
3つのカテゴリーの内容を簡単に確認してみましょう。まず「一般生命保険」は、死亡保障が主な目的で加入者が亡くなった際、遺族に給付金が支払われるタイプの保険です。次に「介護医療保険」は、病気やけがによる医療費負担を軽減するための保険で、がん保険や医療保険がこれに含まれます。
「個人年金保険」は、老後の生活資金を確保するために積み立てる保険です。一定の契約条件を満たせば税控除の対象となります。
実際にどのくらい税金が安くなるのか?

生命保険料控除は、具体的にどの程度の節税効果があるのか気になる人も多いのではないでしょうか。ここでは、控除の上限額や税負担の軽減効果について具体的なシミュレーションを交えて解説します。
控除額の上限と具体的な節税効果
生命保険料控除の適用には、新制度と旧制度があり、それぞれの契約日に応じて控除額が異なります。以下の表で所得税・住民税の新制度と旧制度の控除額をまとめました。
【新制度(平成24年1月1日以降に契約)】
所得税 住民税 年間支払保険料等
控除額
年間支払保険料等
控除額
2万円以下
支払保険料等の全額
1万2,000円以下
支払保険料等の全額
2万円超 4万円以下
支払保険料等×2分の1+1万円
1万2,000円超
3万2,000円以下
支払保険料等×2分の1+6,000円
4万円超 8万円以下
支払保険料等×4分の1+2万円
3万2,000円超
5万6,000円以下
支払保険料等×4分の1+1万4,000円
8万円超
一律4万円
5万6,000円超
一律2万8,000円
※所得税の場合、一般生命保険料控除・介護保険料控除・個人年金保険料控除で各4万円が上限(3つの合計で最大12万円)
※住民税の場合、一般生命保険料控除・介護保険料控除・個人年金保険料控除で各2万8,000円が上限(3つの合計で最大7万円)
【旧制度(平成23年12月31日以前に契約)】
所得税
住民税
年間支払保険料等
控除額
年間支払保険料等
控除額
2万5,000円以下
支払保険料等の全額
1万5,000円以下
支払保険料等の全額
2万5,000円超 5万円以下
支払保険料等×2分の1+1万2,500円
1万5,000円超 4万円以下
支払保険料等×2分の1+7,500円
5万円超 10万円以下
支払保険料等×4分の1+2万5,000円
4万円超 7万円以下
支払保険料等×4分の1+1万7,500円
10万円超
一律5万円
7万円超
一律3万5,000円
※所得税の場合、一般生命保険料控除・介護保険料控除・個人年金保険料控除で各5万円が上限(3つの合計で最大10万円)
※住民税の場合、一般生命保険料控除・介護保険料控除・個人年金保険料控除で各3万5,000円が上限(3つの合計で最大7万円)
たとえば各保険の年間支払金額が以下のとおりだとします。
【新制度(契約日が2012年1月1日以降)】
保険の種類
年間支払い保険料
一般生命保険
3万円
介護医療保険
4万円
個人年金保険
5万円
【旧制度(契約日が2011年12月31日以前)】
保険の種類
年間支払い保険料(円)
一般生命保険
5万円
個人年金保険
4万円
この場合、生命保険料控除額の合計は、所得税で最大11万円、住民税で最大7万円の控除となります。
【生命保険料控除額のシミュレーション結果】
保険の種類
所得税
(新制度)
所得税
(旧制度)
住民税
(新制度)
住民税
(旧制度)
一般生命保険控除額
2万5,000円
3万7,500円
2万1,000円
3万円
介護医療保険控除額
3万円
-
2万4,000円
-
個人年金保険控除額
3万2,500円
3万2,500円
2万6,500円
2万7,500円
合計控除額
11万円
7万円
すでに加入している保険を見直してみよう
生命保険加入者は、現在の契約内容が生命保険料控除の対象となっているかの確認が重要です。また生命保険料控除枠を最大限活用できているかチェックし、枠が余っている場合は適用可能な保険を追加で検討するのもよいでしょう。
たとえば、「一般生命保険には加入しているが介護医療保険には未加入の場合、追加で医療保険に加入することで控除枠を有効活用できる可能性がある」といった具合です。なお保険の見直しは、節税と保障のバランスを考えながら行いましょう。
生命保険を資産形成の視点で考える

生命保険は、資産形成の観点からも重要な役割を果たします。万が一の保障や老後の生活資金の確保といったメリットを最大限に活用するために生命保険をどのように選ぶべきかを再確認してみましょう。
将来の備えとしてのメリット
生命保険は、たとえば老後資金の準備に適した「個人年金保険」や万一の際に家族を支えるための「死亡保障保険」など、それぞれのライフステージに応じた適切な保険選びが重要になります
「節税+保障」の両方を意識した選び方
生命保険を選ぶうえで重要なのは、自分や家族の将来にとって最適な保障内容を持つ商品を選ぶことです。たとえば扶養家族がいる場合は死亡保障の充実が求められますが、独身者や自営業者の場合は老後資金の積み立てがより重要となります。また、保険の加入状況によっては、控除の最大枠を活用できていないケースもあるため、一度契約内容を確認することをおすすめします。
まとめ
生命保険料控除をうまく活用すれば税負担を軽減しながら将来の備えを強化することができます。
【ポイントの整理】
1.生命保険料控除を活用すると所得税・住民税の負担が軽減される
2.一般生命保険・介護医療保険・個人年金保険の3つの枠を活用すると新制度は最大12万円、旧制度は最大10万円の控除が適用可能
3.節税だけでなく将来の保障や老後資金の準備としても生命保険を活用できる
すでに加入済みの保険の見直しや新たな加入をしましょう。
※本コラムは2025年3月1日時点の税制の内容で記載しています。
この記事の執筆協力
- 執筆者名
-
藤森みすず
- 執筆者プロフィール
-
食品衛生管理者、情報処理のアプリケーションエンジニア。21年ほどメーカー系SIerにてプログラマー、システムエンジニアを経験。退職後、Webライターとして様々な分野の執筆を行う。一時期、飲食業開業について学んだことがあり、起業関連の情報にも精通。FXなど投資関連も得意とする。
- 募集文書管理番号